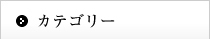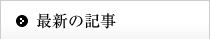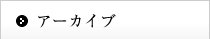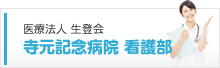こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
今年は冬の初めから厳しい寒波が訪れ、身体をちぢめて過ごしていました。
皆様、風邪など引かれていませんか?
私はいち早く引いてしまい、今回はノド風邪で声が出ない一週間を過ごしました。
未だにノドの調子が芳しくない状態です。
皆様もお気を付け下さい。
さて、今回は一年を振り返り、印象に残っている支援の一例をご紹介したいと思います。
私たちケアマネージャーは介護保険利用のサービスを提供するだけでなく、公的サービス、民間サービスといろいろな情報を集め、利用者様にお知らせすることも仕事の一つです。
今年担当させていただいた利用者様が、定期的にデイケアなどに参加することはしたくないが、腰痛があるので痛みを軽減したいと希望されました。
そこでます、地域包括支援センター ⇒ 保健所 ⇒ 民生委員へと問い合わせをし、情報を集めました。
すると、地域の集会場で『元気アップ体操』を月一回のペースで行っていることが分かりました。
これなら顔見知りの方もおられ、参加しやすいのではと思い提案をさせて頂きました。
とりあえず、どんなものかと参加してみる事となり、ケアマネージャーも同行させて頂きました。
近くの集会場で1時間~1時間30分程度で、全員がバイタルチェックをしてから参加します。
前半・・・保健師さんから食事についての話(河内長野市食育推進計画)
後半・・・デサントヘルスマネジメント研究所の指導員さんが《もの忘れ予防》について話をされ、“頭の体操”をしました。
●もの忘れ?それとも認知症?
【老化に伴うもの忘れ】
・体験の一部
・もの忘れ状態を自覚できる
・家族、自宅の場所、季節を意識している
【認知症によるもの忘れ】
・体験そのものを忘れる(食事など)
・もの忘れの状態を自覚できない
・家族、自宅の場所、季節が分からなくなる
●日常生活から予防しましょう!
【日記をつける】
簡単な日記でもかまいません。まずは、その日の出来事をメモ感覚でつけてみましょう。
【家事】
洗濯しながら掃除をしたり、煮物をしながらサラダを作るなど、二つのことを同時にやってみましょう。
【段取りを立てる】
買い物や仕事などは段取りを立ててから着手しましょう。
旅行の計画を立ててみましょう。
●脳を使って考え、脳の血流を良くし、活性化することが大切です。
【かなひろい問題】
「読む」「文字を拾う」の二つの仕事を行います。
●運動で脳の血流を良くしましょう!
ウォーキングなどの有酸素運動は脳の血流を増加させます。
毎日30分くらい、やりやすい時間帯に行うのがオススメです。
●五感を通して脳を刺激!
・景色を見る
・花の香りをかぐ
・風を肌で感じる など
●歩きながら計算してみましょう!
●頭の体操
【グーパー】
胸の前でグーパーを交互に入れ替える
【一人じゃんけん】
右手に勝つように左手を出す。
次は負けるように出す。
【ネコとネズミ】
ネコ役とネズミ役を決める。
向かい合わせに座り、「ね、ね、ねー・・・ネコ」と言った場合、ネコの人がネズミの人の手をたたき、ネズミの人はたたかれないように逃げる。
「ネズミ」と言った場合は立場が逆になる。
皆様の地域にも民生委員、自治会主催で『元気アップ体操』のようなイベントを開催されていると思います。
参加してくださった利用者様は、楽しんで参加してくださいました。
積極的ではなかったのですが、次回も参加してくださるとのことで、少しでも体を動かす機会ができ、腰痛予防になればと思っています。
後日、参加していただいたか電話で確認をさせていただきましたが、残念!!腰痛で参加できなかったとの事。
次回(2月12日)にまたお誘いしようと思っています。
いろいろと情報を取得し、支援できればと考えています。
本年もありがとうございました。
よいお年をお迎えください。
2014年12月30日
12:30 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
今日は救急時の対応方法についてお話をさせていただきます。
ということで・・・こんな時はすぐに救急車を呼びましょう!
~症状~
【顔】
顔の半分が動きにくい。
笑うと口や顔の片方が歪む。
ろれつが回りにくく、上手く話せない。
視野が欠けたり、突然物が二重に見える。
明らかに顔色が悪い。
【頭】
突然激しい頭痛がする。
急に高熱が出る。
立っていられないほどフラつく。
【手足】
突然片方の足や腕に力が入らなくなる。
突然手足がしびれる。
【腹】
突然の激しい腹痛。
持続する激しい腹痛。
嘔吐・下血
【胸・背中】
急な息切れ・呼吸困難。
突然の激痛。
胸の中央が締め付けられるような、又は圧迫されるような痛みが2~3分続く。
激しく痛む場所が移動する。
【その他】
呼びかけても返事がない。
けいれんが止まらない、あるいは止まっても意識がない。
冷や汗を伴う強い吐き気。
食べ物を喉に詰まらせ、呼吸が苦しかったり意識を失っている。
広範囲に火傷を負ったり、大量の出血を伴う外傷がある。
交通事故で強い衝撃を受けた。
高いところから落ちた。
水に溺れている。
~救急車を呼んだら用意しておくと良い物~
保険証や診察券。
普段飲んでいる薬・お薬手帳。
現金。
靴(裸足のまま搬送されることが多いため)
~急な病気やケガの時に救急車を呼んだ方が良いのか迷った時~
救急安心センターおおさかへ相談を。
#7119 または 06-6589-7119
24時間365日、相談員・看護師が医師の支援体制の下、緊急性の判断や応急手当の方法、近所の救急病院の案内や緊急性の高い場合には救急車の出動要請等をしてくれます。
救急車の台数には限りがあります。
救急車が本当に必要な人に円滑な対応ができるよう、私たち一人一人が協力し、上手に利用しましょうね。
2014年12月4日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
9月からプレハブへ移転しているケアプランセンター。
未だに時々言われる「ケアプランセンターどこいったの?」
利用者様から「夜逃げしたよ」の一言。
(T△T)
こんにちは、てらもとケアプランセンターです☆
私たちは寺元記念病院駐車場敷地内のプレハブ2階にて、ケアマネージャー14名、介護用品レンタル3名、通所リハビリ受付嬢1名とで頑張っています!!
それでは今回もはりきってまいりましょう!
~私のひとりごと~
悲しい時・・・喉が痛く、声が出ないので静かに過ごしていると「事務所が静かでいいな。」と言われた時。
嬉しかった時・・・寺元記念病院での献血日、ケアプランセンターからも何人か申し込んだが、体重等の検査をパスして献血できたのは私だけ。
おばさんを感じる時・・・テレビは健康番組やダイエット番組にしか興味が向かない。なのに最近、ウエストの位置が分からない。
気を遣う時・・・利用者様が白内障の手術をされて「よう見えるわ」と言われたので、少し距離を置いて話をする。
職場が「すごいな」と感じる時・・・チームてらもとで連携を取り、難しい問題が解決できた時。私が活躍できるのは、、、ごみ捨てかな?∩(^▽^)∩
元気になる時・・・阪神タイガース、クライマックスシリーズ優勝おめでとう!!日本シリーズは残念でした(;_;)
ケアプランセンターの相談窓口は、平日は毎日受け付けています!
寺元記念病院の受付でお声をかけていただくと、すぐに階段を“ダダダッ”と降りてそちらへ参ります。
相談するなら・・・今でしょ!?
2014年11月26日
12:30 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
「暑さ、寒さも彼岸まで」と昔から言われますが、朝・晩は本当に過ごしやすくなりましたね(日によっては寒いくらい!)
朝・晩と日中の気温差が大きく、体調を崩されている方もいらっしゃるようですので、皆さんくれぐれもお気を付けくださいね。
さて、私たちケアマネージャーは今までは寺元記念病院の1階に事務所がありましたが、病院の改装工事に伴い、先月より事務所が移転しています。
とはいっても、同じ病院敷地内のプレハブの2階ですので、すぐにお分かりいただけるかと思います。
ただ、2階に上がる階段は少し急でして、雨の日には足元が滑りやすくなっていますので、ご入用の際は無理をして上がらずに、病院受付のスタッフにお声掛けいただければ私たちが参ります。
なにかとご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
2014年10月20日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは。てらもとケアプランセンターです。
8月も残すところ数日となりましたが、今年の8月は台風が直撃したり、豪雨による災害が起こったり(“平成26年8月豪雨”と命名されたそうです)、なんとなく涼しかったり、ひどく暑かったりと気候の変化が激しい夏でした。
気候の変化は大きなストレス要因といわれており、体調不良や不安感などを招くことがあります。
どの年齢の方にも限らず、みんな元気で過ごしたいものですね。
先日キックス(河内長野市立市民交流センター)で実施された「認知症 キッズサポーター養成講座」のお手伝いに参加させていただきました。
小学3年生~6年生までを対象とした講座で、夏休みの暑い中、子供たちは元気に参加してくれていました。
緊張の中で始まった講座でしたが、時間が経つにつれ、笑顔や笑い声もこぼれだし、“認知症”という難しい課題に真剣に取り組んでくれていました。
認知症という言葉を初めて知った児童も、身近な人に認知症の方がいるといった児童も、みんなが持っている大切なおじいちゃん・おばあちゃんへの思いやりを感じ取れる場面もあり、お手伝いをさせていただいた私のほうが感心した一日でした。
ますます少子高齢化が進む日本(そんな大きな社会の流れは、子供たちにはまだ分からないだろうけれど)
子供たちが認知症という病気のことを考え、思いを言葉に出してくれたことに、高齢者福祉に携わる者として、あるいはそれ以前に一人の人間として、本当に嬉しく思いました。
これもひとえに、保護者の方や学校の先生方の関わり方の賜物であると思います。
―――思いをはせる。
ケアマネージャーとして、とても大切な一面だと思います。
てらもとケアプランセンターでは、14人のケアマネージャーがそれぞれのパーソナリティを持って、ご高齢者本人様やそのご家族様への思いをはせて、より良い関わりが持てるように、今まで以上に心がけていきたいと思います。
まだまだ、子供たちには負けていられませんから(笑)
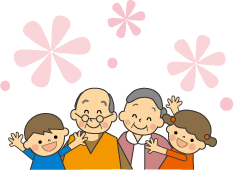
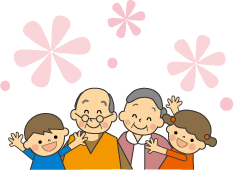
2014年8月27日
11:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
「暑っっつい~(汗」
今年の夏も、毎年恒例の決まり文句を連発しそうです・・・。
それにしても・・・最高気温37℃って!!
人間の平熱を超えています(T△T;;
もともと低体温気味の私には昨年よりも厳しい夏になりそうです・・・。
地球温暖化により気温は上昇していますが、人間の平熱は下がっているというデータがあるそうです。
皆様はご自分の体温を日ごろから計られているでしょうか・・・?
低体温では免疫力が低下していまいます。
逆に、基礎代謝を上げると体温も上がり、免疫力がアップするといわれています。
適度な運動や食事等を改善することで基礎代謝を上げることができますので、暑い夏を乗り切るためにも生活習慣を今一度見直してみてはいかがでしょうか?
私(40ウン歳の(一応)女性ケアマネ)はといえば、7月29日の土用の丑の日に、(念願の)国産ウナギを食べてしっかりとエネルギーを充電☆
来たる暑さのピーク時期に向けて準備万端です!!
さて、てらもとケアプランセンターでは、皆様の在宅介護を支援させていただいています。
特にこの夏場、脱水症や熱中症等で救急搬送されることを未然に防げたら・・・と思いながらご利用者様宅への訪問活動を実施しています。
事業所ではお気軽にご相談いただけるように窓口も設けていますので、今現在介護サービスをご利用されていない方でも、在宅介護に不安を感じること等がありましたら、ご遠慮なくご相談ください。
14名の常勤ケアマネージャーがお待ちしております。
2014年8月5日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは!!
てらもとケアプランセンターです。
穏やかな日々が続き、心も和やかになるような気がするこの頃です。
今回は"骨粗しょう症"をテーマにしたいと思います。
骨粗しょう症(骨の強度が低下し、骨折のリスクが高まる骨格疾患)という病気を皆さん一度は聞いたことがあると思いますが、骨粗しょう症になる原因はご存知でしょうか?
骨粗しょう症は多くの原因が関与して起こる病気です。
「加齢」といった防ぎようの無い原因もありますが、「カルシウムの摂取不足」「運動不足」など、日々の生活習慣を改善することで防ぐこともできます。
カルシウム摂取量の適量は年齢によって変化しますが、70歳以上であれば男性750mg・女性650mgが目安量となります。
1日3食の規則正しいバランスの取れた食事や、牛乳やヨーグルトなどのカルシウムを多く含んだ食品を摂ることが大切です。
また、運動不足解消については、軽いウォーキングや自宅で出来る体操などが良いでしょう。
骨粗しょう症は長年の蓄積によって発症するリスクが高まる病気と言えます。
言い換えれば、出来るだけ早い段階から生活習慣の改善などの予防を行うことで、発症リスクを抑えることができる病気なのです。
家に閉じこもらず、通所系サービスを使って日々の生活を活性化することもまた、生活習慣の改善に大切なことです。
そこで、7月より『生登福祉デイサービスセンター 松葉の湯』がグランドオープンされます。
お食事、入浴、レクリエーション、機能訓練等等、癒しと寛ぎのサービスを提供させていただきますので、ご興味を持たれた方は是非てらもとケアプランセンターへご相談ください!
2014年5月26日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターの髙木です。
先月のブログにて、2月16日(日)に開催される河内長野市シティーマラソンの練習に日々励んでいる旨のお話を致しました。
今回はその結果をご報告させていただきます。
2月16日(日)当日は晴天ながら、14日に見舞われた大雪の影響のため、滝畑エリアが走行困難であるという主催者の判断によりハーフマラソンの部は中止となりました。
よって、ハーフマラソンの部の参加者は10kmコースに振り替えられることとなり、ハーフマラソンにエントリーしていたランナーにとって、今年は少し物足りない大会になってしまったことでしょう。
それではお待ちかねの私個人の結果(成績)ですが、39歳以下男子10kmコース(エントリー数98名)で、タイムは58分30秒!順位は49位でした!!
つまりは、ちょうど真ん中の順位ということであり、なんとも中途半端な結果になってしまいました・・・。
しかし、沿道の方々のあたたかい声援を受け、最後まで走りきったという満足感と爽快感はマラソンに参加した者にしか味わえず、それはタイムや順位には代えがたい感覚であることを再確認することができました。
ちなみに、完走後にいただいた豚汁とバナナは、毎年の事ながら最高に美味しいものでした。
それでは、そろそろ今回の本題に入らせていただきます。
先月、2月26日に天王寺区の大阪国際交流センターにて「キャラバン・メイト養成研修」が実施され、私も参加してきました。
キャラバン・メイトとは、自治体事務局等と協働して地域や職場・学校などで、一般の方々や各種福祉専門職関係者等に対して講座を開き、「認知症サポーター」を多数養成し、認知症になっても安心して暮らせる町を市民の手によってつくっていこうという厚生労働省が推進する活動です。
認知症は誰にでも起こり得る脳の病気に起因するものです。
代表的なものとして「アルツハイマー型」「レビー小体型」「脳血管性」「前頭葉・側頭葉型」があります。
しかし、病気によって認知症の現れ方や症状は様々であり、また個人差も大きくあります。
認知症患者数は2012年で約305万人(厚生労働省発表)、平成37年には470万人にまで増加すると見込まれています。
※2013年6月に発表された厚生労働省研究班の調査では、2012年時点で推定462万人、認知症予備軍も400万人にのぼるともいわれています。
このような背景から「認知症を知り、地域をつくる10ヵ年」のキャンペーンがはじまたっといえるでしょう。
この10ヵ年計画は2005年からスタートし、今年2014年が10年目となります。
キャラバン・メイトもこの10カ年計画の一環として実施されているのです。
認知症サポーターとは何か特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者として、自分の出来る範囲で活動します。
認知症を自分自身の問題と認識し、学んだ知識を友人や家族に伝えることや、認知症の方やその家族の気持ちを理解しようと努めることもサポーターの活動です。
例えば、地域で認知症の人が困っている様子が見えたなら「何かお手伝いすることは有りますか?」と一声かけてみます。
たとえ具体的な援助ができなくても、理解者であることを伝えることはできます。
このような地域で暮らす方々の小さな思いやり、心がけ、温かい見守りが、認知症の方が地域での生活を続けていくうえで大きな支えとなるのです。
他人事として無関心で居るのではなく、「自分たちの問題である」という認識を持ち、自分なら何ができるのかを「認知症サポーター養成講座」に参加し、じっくりと考えてみる機会をつくってみてはいかがでしょうか?
2014年3月26日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
ここ2~3日、河内長野市では日中より雪がちらつくほどに気温が下がり、立春とは名ばかりの寒い日が続いています。
そんな中、2月16日(日)に開催される河内長野市シティーマラソンに向け、日々(といっても3~4日に1回程度ですが)予定されているコースを走り、参加への意識を高めています。
ただし、ハーフマラソンにエントリーする勇気はなく、10kmコースでの参加ですが・・・。
申し遅れましたが、私はてらもとケアプランセンターの髙木と申します。
ケアマネージャーとしてはまだまだ駆け出しの身であり、先輩方の指導を受けながら、担当させていただいているご利用者様の力になれるようにと切磋琢磨の日々を過ごしておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
さて、今回はタイトルのとおり「食事バランスガイド」についてお話させていただきます。
人は加齢に伴い徐々に消化機能・嚥下(えんげ)機能・咀嚼(そしゃく)機能等が低下し、次第に必要な栄養を摂取できない状態に陥ることがあります。
もちろん生活環境による個人差や持病による程度差もありますが、栄養状態の悪い状況が長く続くと、いずれは生命の危機に陥ることはいうまでもありません。
また、近年では20歳代男性の朝食の欠食や若い女性の無理なダイエット、30歳代~60歳代の男性の肥満(メタボリック症候群)等、ライフステージ別の問題点も目立つようになってきています。
「食事バランスガイド」は平成17年6月に厚生労働省・農林水産省が「食生活指針(平成12年3月)」を具体的な行動に結びつけるものとして、食事の望ましい組み合わせや、おおよその量を分かりやすくイラスト化したものです。
食事バランスガイドは次のようなコマの形で表されています。
 日常的に摂取する各料理区分を 「主食」 「副菜」 「主菜」 「牛乳・乳製品」 「果物」 の5つのグループに分け、1日に摂る目安量を“SV”(サービングの略で、料理の単位のこと)で表します。
そして、年齢やライフスタイルに応じて「何をどのくらい食べたらよいのか」の標準的な量を示してあります。
中心となるコマの軸部分は必要な水分量を表し、バランスの良い食事の摂取と適度な運動をすることによって、コマが安定して回るという仕組みです。
※ただし、糖尿病や高血圧等で食事指導を受けている方は医師や管理栄養士の指導に従ってください。
昨年末、東京オリンピック招致決定と並び、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
自然を尊重する日本人独自の精神が表れており、世界の多様な文化の一つにあたると高く評価されたことは、我々日本人にとって大変名誉なことであります。
北から南まで長い日本列島は自然の変化に富み、魚や野菜など四季折々の新鮮な食材をもたらしてくれます。
そして、その新鮮な食材をふんだんに使ったヘルシーで栄養バランスの良い和食は、元来日本人の体に適しており、丈夫で健康な体を育成してくれ、長寿の秘訣であるとも云われています。
若い世代を中心に食生活の欧米化が進む昨今ですが、今一度、日常生活に和食を取り入れ、いつまでも健康でいられる強い体づくりを目指してみませんか?
日常的に摂取する各料理区分を 「主食」 「副菜」 「主菜」 「牛乳・乳製品」 「果物」 の5つのグループに分け、1日に摂る目安量を“SV”(サービングの略で、料理の単位のこと)で表します。
そして、年齢やライフスタイルに応じて「何をどのくらい食べたらよいのか」の標準的な量を示してあります。
中心となるコマの軸部分は必要な水分量を表し、バランスの良い食事の摂取と適度な運動をすることによって、コマが安定して回るという仕組みです。
※ただし、糖尿病や高血圧等で食事指導を受けている方は医師や管理栄養士の指導に従ってください。
昨年末、東京オリンピック招致決定と並び、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
自然を尊重する日本人独自の精神が表れており、世界の多様な文化の一つにあたると高く評価されたことは、我々日本人にとって大変名誉なことであります。
北から南まで長い日本列島は自然の変化に富み、魚や野菜など四季折々の新鮮な食材をもたらしてくれます。
そして、その新鮮な食材をふんだんに使ったヘルシーで栄養バランスの良い和食は、元来日本人の体に適しており、丈夫で健康な体を育成してくれ、長寿の秘訣であるとも云われています。
若い世代を中心に食生活の欧米化が進む昨今ですが、今一度、日常生活に和食を取り入れ、いつまでも健康でいられる強い体づくりを目指してみませんか?
 【食事バランスガイドポスター】←クリックしていただくと農林水産省のサイトに移動します。
そちらでポスターの大きな画像を開くことができますので、是非ご活用ください。
【食事バランスガイドポスター】←クリックしていただくと農林水産省のサイトに移動します。
そちらでポスターの大きな画像を開くことができますので、是非ご活用ください。
 日常的に摂取する各料理区分を 「主食」 「副菜」 「主菜」 「牛乳・乳製品」 「果物」 の5つのグループに分け、1日に摂る目安量を“SV”(サービングの略で、料理の単位のこと)で表します。
そして、年齢やライフスタイルに応じて「何をどのくらい食べたらよいのか」の標準的な量を示してあります。
中心となるコマの軸部分は必要な水分量を表し、バランスの良い食事の摂取と適度な運動をすることによって、コマが安定して回るという仕組みです。
※ただし、糖尿病や高血圧等で食事指導を受けている方は医師や管理栄養士の指導に従ってください。
昨年末、東京オリンピック招致決定と並び、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
自然を尊重する日本人独自の精神が表れており、世界の多様な文化の一つにあたると高く評価されたことは、我々日本人にとって大変名誉なことであります。
北から南まで長い日本列島は自然の変化に富み、魚や野菜など四季折々の新鮮な食材をもたらしてくれます。
そして、その新鮮な食材をふんだんに使ったヘルシーで栄養バランスの良い和食は、元来日本人の体に適しており、丈夫で健康な体を育成してくれ、長寿の秘訣であるとも云われています。
若い世代を中心に食生活の欧米化が進む昨今ですが、今一度、日常生活に和食を取り入れ、いつまでも健康でいられる強い体づくりを目指してみませんか?
日常的に摂取する各料理区分を 「主食」 「副菜」 「主菜」 「牛乳・乳製品」 「果物」 の5つのグループに分け、1日に摂る目安量を“SV”(サービングの略で、料理の単位のこと)で表します。
そして、年齢やライフスタイルに応じて「何をどのくらい食べたらよいのか」の標準的な量を示してあります。
中心となるコマの軸部分は必要な水分量を表し、バランスの良い食事の摂取と適度な運動をすることによって、コマが安定して回るという仕組みです。
※ただし、糖尿病や高血圧等で食事指導を受けている方は医師や管理栄養士の指導に従ってください。
昨年末、東京オリンピック招致決定と並び、「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。
自然を尊重する日本人独自の精神が表れており、世界の多様な文化の一つにあたると高く評価されたことは、我々日本人にとって大変名誉なことであります。
北から南まで長い日本列島は自然の変化に富み、魚や野菜など四季折々の新鮮な食材をもたらしてくれます。
そして、その新鮮な食材をふんだんに使ったヘルシーで栄養バランスの良い和食は、元来日本人の体に適しており、丈夫で健康な体を育成してくれ、長寿の秘訣であるとも云われています。
若い世代を中心に食生活の欧米化が進む昨今ですが、今一度、日常生活に和食を取り入れ、いつまでも健康でいられる強い体づくりを目指してみませんか?
 【食事バランスガイドポスター】←クリックしていただくと農林水産省のサイトに移動します。
そちらでポスターの大きな画像を開くことができますので、是非ご活用ください。
【食事バランスガイドポスター】←クリックしていただくと農林水産省のサイトに移動します。
そちらでポスターの大きな画像を開くことができますので、是非ご活用ください。
2014年2月8日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
お正月も戎祭りも成人式も終わり、一年の始まりが慌ただしく過ぎていきますね。
寒さは厳しく、二十日からは大寒となり、暖かい春が本当に待ち遠しいです。
さて、ケアマネージャーの役割はこれまでの記事を読んでいただければ、だいたいはご理解していただけるかと思いますが、よく『介護保険の要』であるといわれています。
『要』として機能するためには、思いやりがあり、利用者様に寄り添った対応が出来る心豊かな人間でなければなりません。
そういった人間であれるよう、スタッフみんなで切磋琢磨しています(ちなみに、今月は内部研修と外部研修を予定しております)
スタッフ個々の人間味あふれた対応により、介護というものが苦労や大変なことだけではなく、ほっとしたり、時には思わず笑ってしまえるようなこともあるんだと知っていただくことができたら幸いです。
そんな役割を果たせるように、私自身も頑張りたいと思います。
「一年の計は元旦にあり」ということで、さっそく私の今年の目標を書かせていただきましたが、みなさんはいかがでしょうか?
それでは、今年もスタッフ一同がんばってまいりますので、どうぞよろしくお願い致します。
2014年1月17日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター