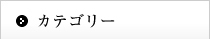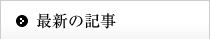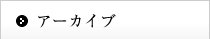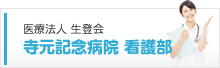こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
12月に入り今週は特に冷え込む一週間となりました。
この近辺では紅葉もピークを過ぎてしまいましたが、京都の北部や滋賀県などでは今が見ごろのようです。
そんな滋賀県にある国宝、彦根城に先月行ってきました。
大阪から第二京阪道路(全線開通からまだ5年ほどの比較的新しい高速道路)を通ると、2時間もかからずに到着できました。
昔と比べて彦根も近くなりましたね。
さて、彦根城は関ヶ原の合戦の後に、徳川家康が豊臣秀吉をけん制するために築かせた、戦のためのお城だそうです。
店主が完成した1607年ごろから幾度の戦災を逃れ、当時のままの姿が残っています。
 例えば、天守までの石段。敵が攻め入ってきても、歩調が乱れて一息で登れないよう、角度や踏み幅などをわざと不規則に造っています。
登のがちょっと大変ですが、400年の歴史に思いを馳せながら歩くのもいいでしょう。
現存する唯一無二の天秤槍は、橋を中心に槍が天秤のように左右対称についていることからその名前がつきました。
敵に攻められた際は、橋を落とし火をつけるそうです。
今も天守に上ることができますが、階段が非常に急です!!
両側に手すりがありますので、上る時はしっかりと握ってくださいね。
女性の方はスカートは避けた方が良いかと思われます・・・荷物はリュックを背負うと良いですよv
宜しかったら参考にしてください!
彦根城と聞いて、もうひとつ忘れてはならないもの・・・
ご存知、ゆるキャラの「ひこにゃん」!!!!
例えば、天守までの石段。敵が攻め入ってきても、歩調が乱れて一息で登れないよう、角度や踏み幅などをわざと不規則に造っています。
登のがちょっと大変ですが、400年の歴史に思いを馳せながら歩くのもいいでしょう。
現存する唯一無二の天秤槍は、橋を中心に槍が天秤のように左右対称についていることからその名前がつきました。
敵に攻められた際は、橋を落とし火をつけるそうです。
今も天守に上ることができますが、階段が非常に急です!!
両側に手すりがありますので、上る時はしっかりと握ってくださいね。
女性の方はスカートは避けた方が良いかと思われます・・・荷物はリュックを背負うと良いですよv
宜しかったら参考にしてください!
彦根城と聞いて、もうひとつ忘れてはならないもの・・・
ご存知、ゆるキャラの「ひこにゃん」!!!!
 決まった時間に広場に出てきてパフォーマンスをしてくれます。
ゆるキャラですので、非常にゆっくりとした動きで可愛らしかったです(*´ω`*)
決まった時間に広場に出てきてパフォーマンスをしてくれます。
ゆるキャラですので、非常にゆっくりとした動きで可愛らしかったです(*´ω`*)
 機会があれば、みんさんも行ってみてくださいね。
機会があれば、みんさんも行ってみてくださいね。
 例えば、天守までの石段。敵が攻め入ってきても、歩調が乱れて一息で登れないよう、角度や踏み幅などをわざと不規則に造っています。
登のがちょっと大変ですが、400年の歴史に思いを馳せながら歩くのもいいでしょう。
現存する唯一無二の天秤槍は、橋を中心に槍が天秤のように左右対称についていることからその名前がつきました。
敵に攻められた際は、橋を落とし火をつけるそうです。
今も天守に上ることができますが、階段が非常に急です!!
両側に手すりがありますので、上る時はしっかりと握ってくださいね。
女性の方はスカートは避けた方が良いかと思われます・・・荷物はリュックを背負うと良いですよv
宜しかったら参考にしてください!
彦根城と聞いて、もうひとつ忘れてはならないもの・・・
ご存知、ゆるキャラの「ひこにゃん」!!!!
例えば、天守までの石段。敵が攻め入ってきても、歩調が乱れて一息で登れないよう、角度や踏み幅などをわざと不規則に造っています。
登のがちょっと大変ですが、400年の歴史に思いを馳せながら歩くのもいいでしょう。
現存する唯一無二の天秤槍は、橋を中心に槍が天秤のように左右対称についていることからその名前がつきました。
敵に攻められた際は、橋を落とし火をつけるそうです。
今も天守に上ることができますが、階段が非常に急です!!
両側に手すりがありますので、上る時はしっかりと握ってくださいね。
女性の方はスカートは避けた方が良いかと思われます・・・荷物はリュックを背負うと良いですよv
宜しかったら参考にしてください!
彦根城と聞いて、もうひとつ忘れてはならないもの・・・
ご存知、ゆるキャラの「ひこにゃん」!!!!
 決まった時間に広場に出てきてパフォーマンスをしてくれます。
ゆるキャラですので、非常にゆっくりとした動きで可愛らしかったです(*´ω`*)
決まった時間に広場に出てきてパフォーマンスをしてくれます。
ゆるキャラですので、非常にゆっくりとした動きで可愛らしかったです(*´ω`*)
 機会があれば、みんさんも行ってみてくださいね。
機会があれば、みんさんも行ってみてくださいね。
2015年12月5日
10:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
朝・夕の寒さがだんだんと厳しさを増し、今年も残すところ2ヶ月となりましたね。
(20代・30代ではさほど感じることのなかった時の流れの速さ・・・切ないなぁ)
体調に注意していきたいものです。
介護保険の制度が2000年(平成12年)に開始されて15年が経ちました。
介護保険のサービスは自分で選択できるサービスであることはご承知の通りです。
もちろん、介護支援専門員(ケアマネジャー)の事業所についても選んでいただくことになっています。
そんな時、何を基準に選ばれるでしょうか?
事業所のネームバリュー?ケアマネジャーの経験?年齢?性別?
私はかれこれ10年以上ケアマネジャーの業務をさせていただいていますが、自分の両親(団塊世代です)には、最後の決め手は「相性」と話しています。
ケアマネジャーに、介護に関してどんなふうに困り、悩み、辛さや切なさを感じているかを理解してもらえたら、そうした状況に適したサービスのマネジメントをしてもらえると思うからです。
そのためには相性が良い方が、より強くそういった心情を掴んでもらえるはずです。(あくまでも個人的な考えですが)
今年は介護保険の改正が4月にあり、利用料金に関しての見直しがされました。
そしてもう一つ、ケアマネジャーの資質向上に向けた見直しもされました。
残念ながら良いケアマネジメントができるケアマネジャーばかりとは限らない現実があることも確かで、ケアマネジャーとして業務に携わる場合、必ず受けなければならない研修が増えたりしています。
より良いケアマネジメントができるということは、「より自分たちの状況を理解し、その状況に合わせたケアマネジメントができる」ということだと思います。
そのためには、やっぱり相性も大事だと思っています。
沢山ある介護支援専門員の事業所、沢山いるケアマネジャーからどう決めていけばいいのか・・・?
いくつか問い合わせの連絡をした中で迷った時には、もしよければ相性も選択の材料とし、検討してみてもらえたらと思います。
2015年11月11日
3:15 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
皆さんこんにちはてらもとケアプランセンターです。
私は7月よりこちらのケアプランセンターに仲間入りしました新人ほやほやの
一年生です。
まだまだ分からないことばかりで、先輩ケアマネジャーに助けてもらいながら
毎日奮闘しております。
てらもとケアプランセンターの皆様は仕事熱心ですが、事務所内は和気藹々として
休憩時間は毎日笑いの耐えないところです。
色んな利用者様とお会いする事でたくさんのことを学び、ケアマネジャーとして
利用者様が何を望んでいるのか、自分はそれにどう対応していくのか、先輩ケアマネジャーの動きを見ながら皆さんの良い所を盗んで日々成長していきたいと思います。
未熟者ではありますが、これからもよろしくお願い致します。
さて、こんな新人の私がこれからスタートしますマイナンバー制度について少し
説明したいと思います。
「マイナンバー制度」
皆さんも何かしら耳にしているかと思いますが、じゃあどんな制度?と思われている方も多いかもしれません。
そこで簡単にまとめてみたいと思います。
マイナンバー制度とは・・・
税、社会保障、災害対策などで法律や自治体の条例で定められた行政の手続きに利用される。
住民票を持つ国民一人ひとりに12ケタの番号が与えられる。
この番号が「マイナンバー」といいます。
今年の10月から住民票の住所へ世帯ごとに簡易書留郵便で送られてきます。
住民登録以外の住所には転送されませんので実際の住所が異なる場合は異動手続きをして下さい。
特別養護老人ホームへ入所の方で住所を変更している方は施設の方に郵送されます。
ショートステイを利用中の方に関しては施設の方にお問い合わせ下さい。
マイナンバー制度になると何が良いのか?
① 申請時に必要な課税証明などの資料の添付を省略出来る。
② 行政機関での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになる。
③ 行政機関が住民の所得状況などを把握し、不正受給を防止できる。
カードが送られてきますので、失くさないようご注意ください。
2015年10月26日
4:00 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは!てらもとケアプランセンターです。
9月13日(日)に河内長野市の恒例行事となりました“第5回いきいき介護フェスタ"へのブース出展も無事終了しました。
足を運んでくださった方がいらっしゃれば、目にしていただいたかもしれませんね。
さて、9月といえば後半に“シルバーウィーク”という大型連休がありました。
「心身ともに良い気分転換がはかれた!」という方や、「いやいや・・・通常通り仕事してましたよ。。。」という方など人それぞれですね(^^;
ちなみに、次のシルバーウィーク5連休は11年後になるとのことです。
最近では9月15日ではなくなってしまった“敬老の日”(・・・覚えやすかったのに)にちなんで、今回は「寿命を延ばすコツ」をご紹介します!
①結婚をし、配偶者と共に生活する(+1年)
②健康的な体重の維持(+6年)
③禁煙する(+10年)
④常に笑うようにする(+8年)
⑤整理整頓を心がける(+1年)
⑥良い物を食べる(+6.6年)
⑦肉の摂取を少なめにする(+3.6年)
⑧ポジティブシンキング(+9年)
⑨信仰心を持つ(+3年)
⑩夜はよく眠る(+5年)
⑪歯磨きをする(+6年)
⑫ペットを飼う(+2年)
⑬女性になる(!?)(+3.3年)
⑭もっと後で生まれる(??)(+6.1年)
・
・
・
実現できるかどうかは別として、どうでしょう?
あまり無理のない身近な範囲でチャレンジできそうなこともありますよね!
日本人の平均寿命は、2014年簡易生命表の概況の統計によれば、男性80.5歳、女性86.8歳!!
いつまでも元気に年齢を重ねていくことができれば素敵ですよね☆
まだまだ介護保険のご利用に抵抗のある方もいらっしゃるかと思いますが、介護サービスを上手に活用して「自分らしい毎日の生活」を楽しんでいきましょう。
介護保険ご利用時の計画書(ケアプランといいます)の作成をはじめとして、煩雑な手続きも代行でお手伝いさせていただけることもありますし、相談窓口も設けていますので、お気軽にお立ち寄りください。
キンモクセイの匂いと共に、朝夕は冷え込みを感じる季節となりました。
お風邪など召されませんように・・・。


2015年9月25日
10:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
皆さん、こんにちは。てらもとケアプランセンターです。
夏真っ只中!!今年は昨年に比べると少しマシなような気がしますが、夏は夏。
じっと座っていてもムシムシして汗ばんできますよね。
年齢を重ねると喉の渇きを感じにくくなるそうです。喉が渇いていなくても適宜水分補給は忘れず行なって下さいね。
そして世の中は節電ムードですが、上手にクーラーを使ってバテないようにしましょう。
節約の点でいうと、クーラーを除湿モードにするより28度位の少し高めの温度設定にして、こまめに消すよりもずっとつけっぱなしのほうが電気代は安くつくそうです。
私はそんなことをつゆ知らず、限界ギリギリまで汗をだらだらかきながら我慢し、その後クーラースイッチオン!20度まで下げて「ホゥ~~~・・・」と弛緩状態。
そのうちだんだん冷えてくるのでクーラーを消す。
そして再び限界ギリギリまで・・・と繰り返していました。
なんということでしょう!!自他ともに認める節約家(ドけち)の私がそんな無駄なことをして電気代を高くしていたとは!!
私には娘が三人いるのですが、彼女らは家計のことなど全く気にせず、シャワーは流しっぱなし、電気はつけっぱなし。
発見するたびギャンギャン注意するのですが、一向に改善のきざしなしです。
以前長女が自室のクーラーをつけっぱなしで、あろうことか旅行へ。
夜中トイレにたった時に、なぜかひんやりする廊下・・・。
冷気は長女の部屋のドアの隙間から。「ま、まさか!?」とドアを開けると真夏の暑い夜に冬のような寒い部屋!!
怒り狂った私はその後約二週間、長女と口をききませんでした。
まあ、たまに私もうっかり消し忘れはありますがそれはそれ。極秘事項です。
彼女らに隙を見せてはいけません。
娘に厳しく自分に甘い、それが私のモットーです(笑
ところで・・・
今年4月から大幅な介護保険法の改正がありました。
そして今月8月1日以降にサービスを利用した時から、一定以上の所得のある方は、サービスを利用した際の負担割合が1割から2割となります。
皆さんのご自宅に市役所から『介護保険負担割合証』はもう届きましたでしょうか?
2割負担となる方は、
① 65歳以上の方で本人の合計所得金額が160万円以上。
② 同一世帯の65歳以上の人(第一号被保険者)の年金収入+その他の合計所得が、単身世帯で280万円以上、二人以上世帯で346万円以上、です。
しかし1割負担から2割負担になった人は全員が月々の負担が2倍になるのではなく、月々の自己負担には上限があります。
上限を超えた分は“高額介護サービス費”が支給されますので、全ての方の負担が2倍になるわけではありません。
でも・・・
今回の改正でやはり今月8月以降に利用したサービスの負担分から《高額介護サービスの基準》が引き上げられることになりました。
特に所得の高い現役並みの所得相当の方のいる世帯については、負担の上限が37200円(月額)から44400円(月額)に引き上げられます。
他対象者については、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合となります。
一般的な所得の方の負担の上限は37200円で、変更はありません。
いずれにせよ、お金に関することはデリケートな問題ですが、避けては通れない大切なことですよね。今月からご注意下さい。
さて、前述の長女による「クーラーまるまる二日間つけっぱなし事件」は怒りのあまり2週間口をきかない母(私)に、謝罪のお手紙とコンビニスイーツを献上してきたので許してあげることにしたのでした。
なんて優しく甘い母なんでしょう。(←ただの現金なやつ
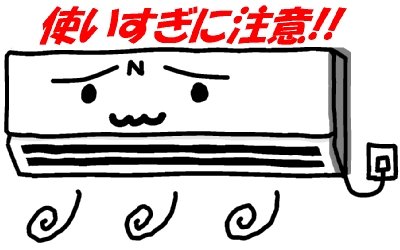
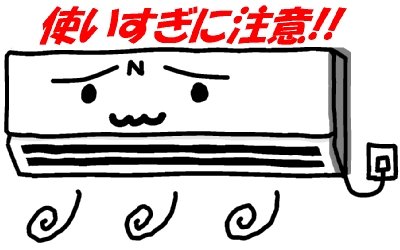
2015年7月28日
9:30 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
小暑を過ぎ、夏本番を迎えようとしています。皆さん体調はいかがでしょうか。
これから益々暑くなり、特に高齢の方は気が付かない間に熱中症に罹る危険性が高くなります。
熱中症予防(対策)のためにも、1日3回のバランスのとれた食事、十分な睡眠、適度な水分補給を心掛け、日頃の健康維持に注意して下さい。
健康維持こそが一番の熱中症対策となります。
さて、本日は社会資源とケアマネージャー、地域包括支援センターの実践についてお伝えしようと思います。
社会資源とは社会福祉の支援過程で用いられる資源を意味します。
一般的に利用者のニーズ(課題)を充足させるために動員されるあらゆる物的・人的資源を総称したものとされています。
それは、各種制度、サービス、人材、組織・団体、活動、情報、拠点、ネットワークなどが挙げられます。
社会資源にはフォーマル(制度的)な社会資源とインフォーマル(非制度的)な社会資源があります。
フォーマルな社会資源とは、法律・制度により基盤が整理されていて、継続性や安定性に優れている面があります。
介護保険制度上のサービスでいうデイサービス、ショートステイ、訪問介護、訪問看護などはそれに該当します。
サービスを利用した際の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割負担となります。
しかし、利用者の対象に制限があること、一定の手続きに基づいて申請し、許可を得て初めて利用が可能となるため、利用者にとって手続きが難しい場合、緊急性がある場合の対応など、個々のニーズに合わせた対応や柔軟性に欠けることがあります。
一方、インフォーマルな社会資源は、民間による自由意思によるものであり、基本的に提供者と利用者の合意によって契約が成立し、サービスが開始されます。
シルバー人材センターによる庭仕事・大工仕事。社会福祉協議会が行うゴミ出し支援。生協などの宅配事業。ボランティアの行う外出への付き添い、見守り、安否確認などがそれに該当します。
サービスには有料の場合と無料の場合があります。
また、対象や利用方法において柔軟かつ即時的に対応しやすいという利点があります。
しかし、利用者が少ない場合や経済的な効率性が悪い場合には、サービスを提供する体制が整わなくなり、安定したサービスの提供が保障されない場合もあります。
地域を基盤としたケアマネージャーの実践では、地域社会のニーズに即して、フォーマル、インフォーマルにかかわらず、既存の資源をいかに有効活用するか、また様々な社資源を個々に対し適切にコーディネートし、いかに適合させていくかが求められます。
更に今後、必要な社会資源が地域に存在しない場合には、地域の福祉課題に応じて、新たなる社会資源を開発するという試みも必要となります。
地域包括支援センターは、地域包括支援体制の実現を目指し、共通支援基盤を構築する機能を担います。
また、市町村には地域包括支援センター運営協議会がおかれ、センターの運営について地域の関係者全体で協議、評価がされています。
つまり、そこで協議されることが地域の意思であり、それに基づいてセンターの活動が行われているのです。
これからの少子高齢社会や経済縮小社会に対する地域社会としての必要な任務は、限られた資源をいかに適切に分配・供給するかを決定し、それを総合的かつ効率的に運用していくかというマネジメントの視点と実施です。
また、地域社会に潜在している資源の発掘や新しい福祉サービスの開発も必須となります。
そしてその評価においては、サービスの効果・効率だけを測定するのではなく、住民参加の意思決定の機会をいかに作り出していけるかがポイントとなります。
2015年7月6日
12:00 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは、てらもとケアプランセンターです。
新緑さわやかな頃もあっという間に過ぎ、夏を思わせる暑さが続きますが、皆さん体調はいかがですか。
今回は五月病についてお話ししたいと思います。
6月に入ろうとしているのに何故この時期に?と思われるでしょうが、最近では、新人研修等が終わり、実務的な仕事に就き始めた6月頃に症状が見られる人が多いことから「六月病」と呼ばれることもあるそうです。
さて、五月病とはご存じの通り、新入生や新卒社員などに見られる“新しい環境に適応できない”ことに起因する精神的な症状の総称で、ゴールデンウィークを境に発症することが多くあります。
ただ、「五月病」は正式な病名ではなく、定義も曖昧です。
そのために「一時的なものだろう・・・」と自己判断してしまい、重度な症状を放置してしまうことで「五月病」の“誤った認識”を生んでしまいがちです。
専門医の間では「無気力症候群」とも呼ばれ、医学的には「適応障害」「気分障害」といった“精神疾患”と考えられています。
そのため、五月病に対する誤解を放置したままにせず、心身の状態と相談し、場合によっては受診する事も大切ではないでしょうか。
軽い症状なら、一日の始まりである朝の過ごし方を工夫すると良いそうです。
関連する記事がありましたのでご紹介させていただきます。
・カーテンを開け日光を入れる
・プロテインを飲む(コーヒー等のカフェインを含むものは良くないそうです)
・炭水化物を食べる(お菓子はNG)
・脂肪の多い魚を食べる(イライラを抑える効果があるそうです)
・散歩をする(気持ちにゆとりが持てます)
これから始まる酷暑、心だけでもさわやかな風が吹くように、五月病(六月病)に心当たりのある方は実行してみてはいかがでしょうか?


2015年5月28日
12:00 PM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちはてらもとケアプランセンターです。
今年の4月はよく雨が降りましたね。楽しみにしていた桜もあっと言う間に終わってしまいました。
昼間は暖かくなってきましたが、朝晩の気温差で体調を崩さないようにしてください。
今年は介護保険の制度改正の年で4月から新制度がスタートしています。
≪介護保険制度改正のポイント≫
一定所得以上の方は介護保険サービスを利用するときの自己負担が2割に(H27年8月から)
①所得が低い方の居住費・食費の負担軽減の要件に預貯金等、配偶者の所得を追加(H27年8月から)
②高額介護サービス費の上限額を引き上げ(H27年8月から)
③70歳未満の方の高額医療・高額介護合算制度の限度額が変更。
④65歳以上で所得が低い方の保険料の軽減割合を拡大(H27年4月から)
⑤「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」を地域支援事業の「新しい総合事業」に移行(H29年4月までに移行)
⑥介護老人福祉施設の新規入所者を原則、要介護3以上に(H27年4月から)
4月から制度が改正になり、私たちケアマネージャーも各事業所もバタバタしておりますが、分からないことがあれば聞いていただければと思っております。
介護保険ではケアプランを作成して、安心して介護サービスを利用できるように支援してもらいますが、ケアプランは人生の設計図。目標達成につながるサービスを組み込むことが大切です。
「担当ケアマネージャーに全てお任せ」ではなくどんな生活を送りたいかや目標をケアマネージャーに積極的に伝えましょう。
サービス利用開始から一定期間後、目標が達成されているか評価します。
サービス途中でも「自分の生活に合わない」「改善が見られない」という場合は、ケアプランの見直しが出来ますので、遠慮なくケアマネージャーに相談してください。
≪ケアマネージャーってどんな人?≫
利用者の希望や心身の状態にあったサービスが利用得切るように導いてくれるサービスの窓口です。
利用者はケアマネージャーを選ぶことができますし、変えることもできます。
その場合は市区町村の介護保険担当の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。


2015年4月25日
9:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
まだまだ寒い日が続きますが、少しずつ木々の芽もふくらみ始めており、春の訪れまでもう一息というところでしょうか。
皆様、お変わりなくお過ごしでしょうか。てらもとケアプランセンターです。
今回は、病気や加齢のせいで家事援助や身の回りの世話が必要となり、介護保険のサービスを利用したいと考えておられる方に、利用までの手順についてお話します。
「デイサービスに行きたい」
「ヘルパーさんに来てもらいたい」
「ショートステイを利用したい」
「ベッドを借りたい」
などなど・・・
①まずは「要介護認定」を受けましょう
申請は市区町村の介護保険の担当課です。
申請は本人や家族が行いますが、地域包括支援センターや居宅のケアマネージャーでも代行が可能です。
・申請に必要なもの
申請書・・・介護保険の担当課にあります。
地域包括支援センターやケアマネージャーも用意できます。
介護保険の保険証・・・満40~64歳の方は健康保険の保険証が必要です。
②「認定調査」を受けます
申請すると訪問調査の後に審査・判定が行われ、要介護度が決まります。
・訪問調査とは
調査員が自宅や入院先の病院を訪問し、心身の状態や生活状況等についての聞き取りと動作確認を行います。
・主治医に意見書を書いてもらいます
市区町村の依頼で、主治医が意見書を作成します。
③自宅に結果が届きます
申請から原則30日以内に認定結果が届きます。
要介護1~5・・・介護サービスが利用できます。
要支援1~2・・・介護予防サービスが利用できます。
非該当(自立)・・・地域支援事業が利用できます。
④サービスを利用しましょう
要介護1~5と認定された方は、ケアマネージャーに希望を伝えてケアプランを作成し、介護サービスを利用します。
要支援1~2と認定された方は、地域包括支援センターに連絡し、介護予防プランを作成し、介護予防サービスを利用します。
サービスには、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、通所サービス、ショートステイ、福祉用具レンタルなどの他、特定福祉用具購入や住宅改修などもあり、あなたの介護度に応じて利用することができます。
当事業所でも、月~土まで毎日いろいろなご相談に応じています。
相談担当のケアマネージャーが分かりやすく説明いたしますので、どうぞお気軽にお尋ねください。
2015年2月24日
10:00 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター
こんにちは。てらもとケアプランセンターです。
2月3日は節分でしたが、皆さんのお宅では、豆まきはされましたでしょうか。
最近は、豆まきよりも関西では、恵方に向かってお寿司の丸かぶりという方が多くなってきているようですが、我が家でももう何十年と豆まきをしたことがなく、娘の記憶にもない状態です。
毎年、母が巻きずしを作ってくれていたのですが、高齢に伴い、「今年は、作るのはもうしんどいわ。」と言うので、買ってくることにしました。
予約をしていなかったので、何とかスーパーで手に入れたお寿司を食べる事になりました。
いざ食べようとすると私は恵方を把握していなかったので、母に聞くと母が、「西北・・な・・・とか言っていた。」というので、私が「北北西か。」と言うと「神戸の方に向かって食べたらええねん。」とてきとうな返事。
という事で、そちらに向かって戴きました。
しかし、娘が帰ってきて、そのことを言うと「違うよ。そんな方向じゃなかった。」と。
早速調べると、西南西。
全く違う方向を向いて食べていました。
その日は昔のように豆まきをする事も、一人ずつ豆を取り分ける事もなく母は寝てしまったので、私達だけで年の数だけ豆を食べました。
昔は、本当の大豆を煎った硬い豆だったけど、今は、とても食べやすい。あっと言う間に食べてしまいました。
翌日母が、夕べ豆を食べるのを忘れて寝てしまったと言い、食べようと数えると70個しかなかったというのです。
母は今年、年女。全然足りません。
邪気を払う事も出来ず、今年の母の節分は、なんのご利益もない散々なものとなってしまいましたが、何とか、一年健康に過ごしてほしいものです。
ところで、高齢者にとって歳の数だけ豆を食べるのは、大変な事です。
煎り豆は噛むほどに口の中の水分を奪い、飲み込むときに変なところに入ってむせてしまったり。
縁起物だと年の数だけ食べようと頑張ってしまう方もいるでしょうが、くれぐれも気を付けてください。
“いざ”に備える学びを!!
窒息を起こし、顔色が真っ青になったら咳をさせると解消できるけど、高齢者は咳をする力が弱く、なかなか吐き出す事が出来ません。
万一、詰まった時には迅速に異物を取り除いてあげる事が肝心です。
異物除去の為の簡単な方法が新聞に載っていたので紹介しておきます。
まずやるべきは、背中をたたいて出す、「背部叩打法」
手の付け根あたりで、肩甲骨の間を下からたたきあげるように強く、迅速にたたく。
相手が体を起こしている場合、相手の背後から自分の片手を相手の脇の下に入れ、その手で下顎の部分を支えて顎をそらせて反対の手でたたく。
倒れている場合は、相手の横に座り、自分の方を向くように横向きにし、背中を強くたたく。
異物除去の前には、119番通報も忘れずに。
2015年2月10日
10:02 AM |カテゴリー:
てらもとケアプランセンター